これまで私は価格が下がった時に買う「ナンピン」で投資をしてきましたが、最近、タイミングを見計らわずに投資する「ツミレバ」に興味を持ち、自身の投資法との差が気になっています。
そこで、これまでのナンピン投資の実績と、その投資を毎日「ツミレバ」していたときの運用実績の差をシミュレーションすることにしました。
対象とするレバレッジ銘柄は、私が楽天証券で投資する「楽天レバナス」です。

私が初めて楽天レバナスを初めて購入したのは2022年1月頃でした。
レバナスの基準価格は、2021年11月22日頃に付けた高値から、2022年末にかけて最大で約64%も下落している投資です。
つまり、私が購入を始めた頃からちょうど下落が始まっています。
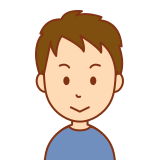
この記事では、大暴落中の「レバナス」を「下落時にナンピン買い」していた方が良かったのか、それともタイミングを見計らわずに「毎日ツミレバ」した方が良かったのか、シミュレーションしてみました。
レバレッジ商品で積立投資(ツミレバ)を考えている方、参考になれば幸いです。
ツミレバとは
最近話題の「ツミレバ」とは、レバレッジ型の投資信託で積立投資をする運用手法です。
多くのレバレッジ取引で借金する理由の一つに「追加証拠金」があります。
証拠金は、急激な相場の変動で維持率を下回ると追加の保証金(※追証)が必要となり、大きなリスクとなります。
しかし、ツミレバは追加証拠金等の心配もなく、追証の心配がないため、最悪の場合でも投資元本がなくなる(ゼロになる)だけで済むので、リスクが限定的です。
では、そんな魅力を感じるツミレバ、これまで私が投資をしてきた「楽天レバナス」で行っていたら、現在どうなっていたのかをシミュレーションしてみました。
ツミレバをシミュレーション
まず簡単に、私の投資実績である「ナンピン」投資と、これからシミュレーションする「ツミレバ」投資の前提条件を整理します。
前提(ナンピン、ツミレバ)
シミュレーションは、楽天証券の特定口座では「楽天レバナス」を毎日積立することができないため、毎日スポットで購入する前提でシミュレーションします。
- 投資対象: 楽天レバナス(NASDAQ100指数連動型)
- 投資期間: 2022年1月6日 ~ 2022年10月19日
- ナンピン: 私の投資実績
- ツミレバ: 毎日、同額の積み立てを想定
もし、楽天証券の口座にこだわりがなければ、SBI証券を使えば毎日のツミレバが可能です。
ただ、その場合、SBI証券では楽天レバナスの取り扱いが無いため、同じ値動きをする別のレバナス(例:iFreeレバナス、auレバナス)による投資となります。
楽天レバナスのスポット買い実績は、以下の投資記事の内容になります。

ツミレバシミュレーションの毎日の積立額ですが、積立金額は投資額のトータルを投資期間の日数(※2022年01月06日~2022年10月19日)で割って算出しました。
積立の総額は190,135円で、期間の中で投資できる日数は192日なので、計算の結果、一日あたり990円の投資となります。
シミュレーション結果
それでは、実際のシミュレーション結果を見ていきましょう。
検証はExcelを使って行いましたが、すべてのシミュレーション結果を掲載するとかなりの行数になるため、途中を省略します。
| 日付 | 基準価格 | ツミレバで投資した場合 | スポットでの購入実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資額 | 口数合計 | 平均取得価格 | 投資額 | 口数合計 | 平均取得価格 | ||
| 2022/01/06 | 9,248.00 | 990 | 1,070 | 9,252.33 | 1,000 | 1,081 | 9,250.69 |
| 2022/01/07 | 9,239.00 | 990 | 2,141 | 9,248.01 | – | 1,081 | 9,250.69 |
| 2022/01/11 | 9,061.00 | 990 | 3,233 | 9,186.51 | – | 1,081 | 9,250.69 |
| ・・・ | |||||||
| 2022/10/18 | 4,079.00 | 990 | 323,768 | 5,840.29 | 948 | 313,541 | 5,808.96 |
| 2022/10/19 | 4,139.00 | 990 | 326,159 | 5,827.83 | 8,000 | 332,869 | 5,712.00 |
最後まで計算した後、10/19時点の基準価格(※4,139円)で時価総額を求め、損益を計算しました。
その結果、私の投資したナンピン買いのタイミングが思ったより良く、平均取得額をうまく下げられていたので、毎日ツミレバよりも私のナンピン実績の方が運用成績が上という結果となりました。
| 時価評価額 | 損益額 | 利益最大時 | 損失最大時 | |
|---|---|---|---|---|
| レバナス「ナンピン」 | 137,774円 | -52,361 | 16,636円 | -62,458円 |
| レバナス「ツミレバ」 | 134,997円 | -55,138 | 5,593円 | -65,508円 |
ツミレバ検証による結論
価格が下がったタイミングで買う「ナンピン」投資と、毎日一定額を買う「ツミレバ」投資のシミュレーションをした結果、私はたまたま買いのタイミングがよく平均取得価格を下げられましたが、毎日値動きを追いながらタイミングを見計らって投資するだけの差を感じませんでした。
また、購入タイミングの誤りや大幅下落時の精神的なショックなどを考えると、ツミレバの投資の方が私に合っていると思います。
今後は、レバレッジ銘柄への投資は「ツミレバ」にしようと思っています。


では最後に、私が口座開設している証券会社を紹介して終わります。
レバナスを毎日積立するならSBI証券
現在、私は「楽天証券」と「SBI証券」で口座を開設していますが、楽天レバナスを買えるのは楽天証券なので、私は楽天証券でレバナスを購入しています。
楽天証券は楽天経済圏で生活している人はもちろんですが、投資画面の見やすさ・わかりやすさに配慮されている点から、初心者にもおすすめの証券会社です。
しかし、記事の途中で書きましたが、楽天証券では特定口座で投資信託を買うときに「毎日」設定ができないので、楽天レバナスにこだわりがなく、他のレバナス(例:iFreeレバナス、auレバナス)でも良ければ、毎日設定をするなら「SBI証券」で口座開設がおすすめです。
ではまた。

